OPアンプの誤差が分かる場所


■解答
(c)の発生源
図2は,図1のOPアンプから見た差動信号と同相信号を図示しました.
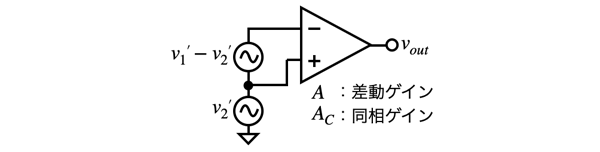
図2 OPアンプに差動信号と同相信号を加えた回路
図2の出力電圧は,「v1'-v2'」の電圧源と「v2'」の電圧源について重ね合わせの理を用いて計算すると,式1になります.
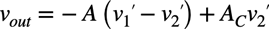 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
ここでAは,OPアンプの差動ゲイン(オープン・ループ・ゲイン)で,ACが同相ゲインです.OPアンプは,反転端子と非反転端子間の電圧差を増幅するアンプですので,差動ゲインのAが高く,同相ゲインのACが低いほど特性が良いアンプになります.
CMRは「C=A/AC」の関係があるので,式1の右辺第二項の「ACv'2」を差動ゲインのAとCMRのCを使って書き直すと式2になります.
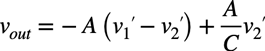 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
式2の右辺第一項の「-A(v1'-v2')」は,OPアンプとして欲しい特性を表し,右辺第二項の「Av2'/C」は誤差項になります.この誤差項をOPアンプの外に出し,等価的に,差動ゲインAとCMRのCを使って図2を書き直すと,等価回路は図3になります.
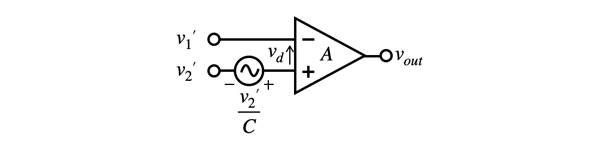
図3 誤差項をOPアンプの外に出した等価回路
「v2'/C」の誤差項は非反転端子に見える.
「v2'/C」の誤差項は非反転端子に見える.
確認のため,図3の出力電圧を机上計算して,式2と比べます.出力電圧は反転端子と非反転端子間の差電圧(vd)をOPアンプの差動ゲインで増幅した電圧なので,式3になります.
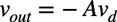 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)反転端子と非反転端子間の差電圧(vd)は式4になります.
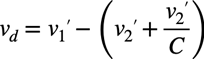 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
式4を式3へ代入して整理すると式2と同じになるので,机上計算からも図2と図3は同じになるのが分かります.以上の検討より,図1のOPアンプを図3の等価回路に置き換えると,「v2'/C」は(c)の発生源の位置に見えることになります.











